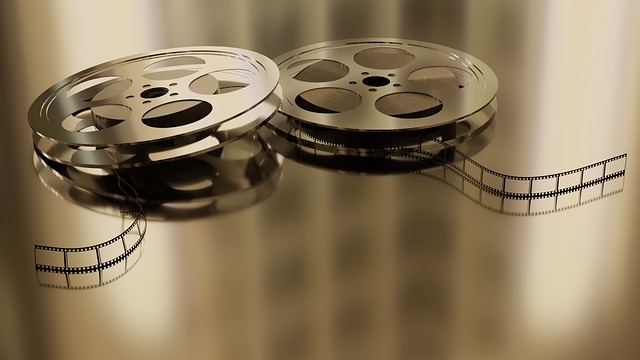
映画館に観に行った映画で最古の記憶は『長靴をはいた猫 80日間世界一周(1976年)』で、それは家から歩いて行ける距離にある町の小さな映画館だった。ジュール・ヴェルヌの『80日間世界一周』を読んだのが2024年2月4日~2月21日(なんでもエクセルに記録する)で、その時に思い出した。
はじめてバスに乗って隣町のもっと大きな映画館まで行ったのは、たぶんドン・コスカレリ監督の『ファンタズム(1979年)』が最初で、重い棺を軽々と持って運ぶシーンと、映画館に向かうバスの中で握りしめたアルミニウムの手すりの感触だけが今も記憶に残っている。
残念なことに1977年の『スター・ウォーズ』をリアルタイムで観ておらず、人生で最も後悔したことになった。『ピンク・レディーの活動大写真(1978年)』などをみてよろこんでいる場合ではなかった。
その頃の地方の映画館は、入替制でもなく席の指定もなく、1枚のチケットがあれば1日中でもいることができた。宮崎駿監督の『風の谷のナウシカ(1984年)』は映画の途中から入場し、意味が分からないまま1回目が終わり、冒頭からもう一度見ようと思ったが、そのためには同時上映されている大林宣彦監督の『少年ケニヤ』を待たなければならなかった。東京なら『劇場版名探偵ホームズ』とバンドルされるべきところ、新潟県三条市では『少年ケニヤ』だったのだ。
2度目(冒頭から観るのは1度目)の『風の谷のナウシカ』を観終わったとき、劇場内は席を立って出口に向かう人の流出と、次の回を観るために席を確保しようとする人の流入がごった返し交錯する中、ぼくは背筋に戦慄が走り、全身の血液が凍り付いたようになって、立ち上がれなくなっていた。
映画の最後、カメラは腐海の底を映し、砂の上に落ちているナウシカのフードにズームする。流砂にのまれたときに落としたものだ。そのすぐそばで植物が芽を出している。これは、ナウシカが風の谷からトルメキアに連れていかれるときに子供たちにもらったチコの実であり、アスベルをヘビケラから助けて流砂にのまれたときに、袋の中から零れ落ちた一粒が、腐海の底の砂から芽を出した、ということなのだ。
腐海は人間にとって住むことのできない世界だが、人間の汚した世界を浄化する作用があり、腐海の底には生きるもののいない死の世界であるものの、きれいな水と砂と空気のある世界で、大木は枯れても水を通している。
そこに持ち込まれたチコの実が芽を出したという事実は、腐海の拡大により居場所のなくなった人間がやがて絶滅し、既存の世界が終焉しても、次の世代のいのちがその小さな一歩をあゆみはじめた、という意味であり、そのあまりに巨大な摂理、もしくは願い、がそのあまりに控え目で目立たない小さな植物の発芽という表現によってさりげなく示された。
だから腰が抜けたのである。
新潟市の万代シティではじめて女性と映画に行ったのは高校生のとき(1986年)で、『バタリアン』と『コマンドー』の同時上映だった。『バタリアン』は最高に面白いと思ったのに、相方には理解されず、途中で席を立って劇場を出て行った。彼女を追いかけるかどうかだいぶ迷った。結局追いかけたが、『バタリアン』を面白く思えない人は話にならないと思った。
同じく1986年は、『天空の城ラピュタ』があり、このへんから映画は2本立てではないのが当たり前になっていった気がする。
英国がスペインの無敵艦隊を破ったのは1588年で、エリザベス女王が即位した30年後だった。当時の英国は経済的にも軍事的にも強力だったが、文化的にはルネサンス発祥のフィレンツェには劣っているという劣等感もあり、お金持ちの貴族は子弟にヨーロッパ大陸への旅行を行わせた。これが17世紀の英国で流行ったグランドツアーで、目的地はイタリアのフィレンツェ、目的は古典的教養の修得である。
でも実際は、目的地のフィレンツェの大聖堂や宮殿に到着する前の、アルプス山脈を越えるプロセスにこそ新しい体験があった。今まで慣れ親しんだ「美」ではなく、それまで経験したことのない新しい「美」を発見することになる。
英国はある程度hilling(この英語は存在しないかも)で、なだらかな丘はあってもたいがいflatな地形である。一方、アルプス山脈は4,000m級の山であり、険阻で急峻、一歩足を踏み外せば断崖絶壁で命はない。オオヤマネコも熊も出るし、夜になれば狼も出る。空にはイヌワシが獲物を狙って旋回している。しかしそんな世界だからこそ、いままで経験したことのない、恐怖を伴う「荘厳な美」を発見した。
グランドツアーの一行はこの感動を英国に持ち帰ったが、英国内に同様な経験のできるスポットはないかと探した。宗教改革(ローマ・カトリックからの分離・独立)から200年近く経過して、いい具合に朽ち果てて廃墟となった教会や修道院、城などが国内に散在していたので、ここに恐怖を伴う「荘厳な美」の疑似体験が可能だった。
なにしろ長い時間が経過しており、風雨にさらされ、火事で焼失し、建物は崩壊し、均整も失われ、左右対称でもなく、つた植物が絡まって、瓦礫と化し、同時に自然に帰ろうとしている。そうした建物は、向き合う人の意識を過去に向けさせ、長い時間の経過を実感させる。
マシュー・グレゴリー・ルイスの小説 “The Monk”(本当はホレス・ウォルポールの“The Castle of Otranto”と云いたいところだが、それは読んでない)あたりからはじまるゴシック小説の要素となった。
メアリー・シェリー“Frankenstein”、ブラム・ストーカー” “Dracula”、ロバート・ルイス・スティーヴンソン “Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”などなど、怪物、幽霊、古城、廃墟、怪奇、監禁、二重性、死、恐怖、過去、強力などのモチーフを持つ。
かくして原宿のゴスロリ(ゴシック・ロリータ)も、恐怖を伴う、死を感じさせる美であるのだ。
そういう視点でみると、宮崎駿監督『天空の城ラピュタ』は、一歩足を踏み外せばたちまち命はない、非常に垂直方向の広がりを意図した場面構成が随所に見られ、城は廃墟と化しており、蔦植物に覆われている。登場するロボットは片腕がなかったりして左右非対称で均整がとれていない。シータは監禁され、ラピュタの力は強大で、向き合う人の意識を過去に向けさせる。安全で小さくてかわいいものにある美ではなく、危険で巨大で荘厳で、恐怖を伴う美、きわめてゴシック的な、死と隣り合わせの美しさが表現されている。
17世紀の英国で流行ったグランドツアーは、1986年のこの映画に影響を与えたのだ。